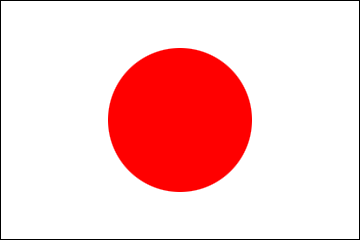済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台
令和3年6月25日
「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
 |
 |
今回は、井関至康総領事と「チルモリ堂霊登クッ」を視察し、ご説明いただいた文化人類学者の玄丞桓(ヒョン・スンファン)済州大国語教育科教授に、済州島にある「堂」をご案内いただきました。
済州の「堂」を訪問
高い「神口密度」を誇る済州だけあって、神様を祀る「堂」の数も多いです。玄丞桓教授のお父様である故・玄容駿(ヒョン・ヨンジュン)済州大教授が1985年に日本で出版された『済州島巫俗の研究』によれば「行政区域215里に平均1.3個ずつ」、済州道の2009年の調査では359ヶ所が活用されているとされています。韓国の本土でも「堂」が南部を中心に分布していたのが、近代化の流れの中で多くが失われてしまった一方で、済州ではこれだけの「堂」と伝統的な民間信仰が綿々と維持されてきていることには、改めて驚きを感じます。今回、改めて済州の「堂」を訪問して、神様の存在や伝統的な信仰を深く感じるという点で、日本の鎮守の森や、沖縄・奄美の御嶽との類似性を実感しましたが、玄丞桓教授によれば、済州の信仰と、日本の本土や沖縄・奄美のそれとは、仏教・儒教との関わり、政治体制の関わり、男女の役割分担という点で、似ていながらも相違点もあるということです。
済州の民間信仰と構造物・男女の役割分担
まず、済州の場合は、もともとあった土俗信仰をベースに、韓国本土から入ってきた仏教の影響が加味され、さらに13~14世紀に元の直接支配を通じてモンゴル仏教の影響も受けるようになりました。その後、朝鮮王朝の下で、国教である儒教の普及が図られ、女性社会が「堂」を中心とする在来の巫俗信仰に依存する一方で、男性社会では「酺祭壇(ポジェダン)」を中心に儒教式儀礼に依存するという、民間信仰の二重構造現象が生まれるようになったとのことです。結果として、「堂」の形態も素朴なものに留まり、構造物といえばせいぜい小さな祭壇や祠があるくらい、となっています。日本の民間信仰と構造物・男女の役割分担
次に日本の本土ですが、6世紀頃とされる仏教の伝来とともに、当初は現在の神道につながる土俗信仰との競合が起こりましたが、8世紀の奈良時代以降、次第に神仏両方とも信仰する方向に進み、習合されるようになります。10世紀には『延喜式神名帳』で、朝廷によって全国の主要な神社がリスト化されるに至ります。また、神道の教義や神社の構造物の形態についても、仏教との相互作用で高度化した面も見られるということです。女性の役割については、古代の卑弥呼の例は言うに及ばず、伊勢神宮や賀茂神社の祭祀に未婚の皇女が奉仕した斎宮の制・斎院の制の歴史を見ても、もともとは非常に大きなものだったと考えられ、現在でも、青森県の霊媒・イタコのような在野の信仰には、女性中心のものも見受けられます。が、現代においては、神社における神事は、男性が多数である神主が主導する場合が多く、巫女さんはどちらかというと補助的役割が多くなっています。
さらに沖縄や奄美の御嶽については、済州の「堂」と同様に、多くの場合、せいぜい小さな祭壇や祠があるくらいです(入口には鳥居がある場合も多いですが)。ところが、琉球王朝においては、政治体制と男女の役割分担については、非常に興味深いことに、国王を頂点とする、男性による中国王朝型の官僚支配体系(儒教が前提とされます)とともに、王族の女性が務める聞得大君(きこえおおきみ)を頂点とし、各村に配備されたノロ(祝女)を末端とする、女性による宗教支配体系が並立して確立されたのです。また、このような体制の外においても、女性霊媒師が主体であるユタが人々に受け入れられ、今に至るまで沖縄や奄美の各地で見受けられます。
済州と日本の神様のあり方は影響し合っている?
以上、玄丞桓教授と「堂」を訪問し、済州の神様を感じたのを機に、日本の本土、沖縄・奄美のそれぞれの神様のあり方との共通点と相違点を考えてみました。互いにどの程度影響し合ったのかについては、諸説ありながらも、分かっていないことも多いようですが、玄丞桓教授のお話しどおり、「済州と日本は、アルタイ・ツングースからの北方の影響、黒潮に乗ってやってきた南方の影響、そして道教の影響がミックスされたアニミズム・シャーマニズムを伝統文化の根底に有するという点で共通しており、また、そのバランスが全体として見ると大変似ている」ということは最低限言えるのでしょう。それぞれの皆さんにとって、それぞれの神様が大事であることは間違いの無いところですが、よそ様の神様に、なんだか懐かしいような親近感を感じるというのも、実は結構すごいことなんだと思われました。訪問関連フォト

△松堂(ソンダン)の「本郷堂(ポンヒャンダン)」
済州に数ある「堂」の中でも、ここは特別な存在。というのも、地元・松堂里の神話(済州では本解=ポンプリと呼ぶそうです)によると、海を渡って済州島に来た女神が産んだ8人の子どもが済州島全体に散らばって各地の堂の神様になったということで、この堂が済州全体の堂の発祥の地だから、ということなんです。いわば「総本山」なんですが、至ってシンプルな構造で、石の壁で背後の森と区切られた手前に祭壇があり、その上に小さな石造りの祠が建てられています(左手には櫓も立っていますが、近年新たに建てられたもので、従来は無かったそうです)。
玄丞桓教授によると、石造りの祠の中には、祭礼で用いられる神様の衣装が折りたたまれて保管されており、梅雨が終わる時期にその衣装を天日で乾かす儀礼が行われるとのことです。また、松堂里は現在は済州島の内陸部に位置していますが、近辺に残された砂や貝殻、さらに海に向かって流れた火山の溶岩洞にある鍾乳石からは、大昔は近くまで海になっており、人々が海を生活の場としていたことが見受けられ、神話で済州の中心と見なされていることとも深い関係があるということです。
なお、近年、済州とは神様の系統が異なるにもかかわらず、韓国本土からわざわざやってきた皆さんがここで巫俗を行うようになり、本郷堂を大事に守ってきてこられた地元の皆さんが迷惑を被るようなケースも出てきたということで、そのような行為は禁止されているとのことです。

△臥屹(ワフル)の「本郷堂」
もう1ヶ所、臥屹里の本郷堂も訪問しました。樹齢400年を超えるという榎の大木が印象的ですが、火災・落雷による樹勢の劣化等の事情により、現在は特別な場合を除き立入り禁止となっているということで、敷地の外からご案内いただきました。かなり広い空間ですが、上記のとおり、松堂の本郷堂から枝分かれしたという位置づけです。榎の幹には色とりどりの布が巻かれており、あたかもご神体を大事に守ろうとしているかのようです。また、木の枝に白い布をくくりつけて祀っていることも観察されましたが、玄丞桓教授からは、日本の神社仏閣でおみくじを木にくくりつけることとの関連も考えられるのではないかとの指摘もありました。

△那智の大滝
日本の有名な神社は立派な社殿を持つところが多いですが、古代から信仰された三輪山をご神体とする奈良県の大神(おおみわ)神社のように、現在に至っても「拝殿」はあるが神様が住まう「本殿」が無いという、古代の信仰の姿を残しているところもあります。また、写真は、済州ともご縁の深い和歌山県にある、有名な「那智の大滝」ですが、実はこの滝そのものが、熊野那智大社の別宮・飛瀧(ひろう)神社のご神体であり、「拝殿」も「本殿」も無く、滝壺の手前から直接参拝します。

△沖縄本島南部の南城市知念に位置する斉場御嶽(せーふぁーうたき)
世界遺産にも登録されている、沖縄を代表する御嶽であり、琉球王国においては最高の神官であり、王族女性が任命された聞得大君(きこえおおきみ)の即位式・御新下り(うあらうり)も行われた聖地です。が、小さな祭壇以外には構造物は見当たりません。

△トルハルバン
済州においては、これまで見てきたように、朝鮮王朝期には、伝統的な巫俗信仰と折衷しながらも国教である儒教を受け入れてきましたが、済州のシンボルである「トルハルバン」は、その逆パターンと考えられるということです。つまり、外部からの厄除けとして家や村の出入口を守る信仰のシンボルであるトルハルバンは、巫俗のご神体だとすると、当然に排斥されるべきものですが、むしろ官が主導して城門の守護神として設置したということは、民間信仰を官が受け容れたものと考えられるということです。外部からの厄除けというと、日本では、木であれば神社の鳥居、石であればお地蔵さんや道祖神が思い浮かびますが、それらとトルハルバンとの関係は、文化人類学的には明確なものにはなっていないそうです。
なお、写真のトルハルバンは、実は済州ではなく、日本の東京都に立っているものです。済州市の友好都市である東京都の荒川区。その区役所の前の荒川公園に、2009年に済州市から贈られた高さ約2メートルのトルハルバン2基が設置されています。(写真提供:栗栖太東京大学准教授・全日本学生競技ダンス連盟会長)
関連記事
・済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00240.html
・済州野焼き祭り~野焼き文化で探る済州と日本のつながり
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html
・ 漢拏山(ハルラサン)~日本の文化人類学のルーツのひとつを訪ねる
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00213.html
・三姓穴(サムソンヒョル)と婚姻址(ホニンジ)~済州誕生神話の舞台で探る日本とのゆかりと共通点
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html
・韓国の国家登録文化財「旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場」~日本で学んだ韓国最高の「蝶博士」にして、済州島研究の先駆者が初代所長
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ko/11_000001_00214.html
・【コラム】ブラブラ歩いて探しました、済州の「OKINAWA」
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00232.html
・済州大学地理教育専攻~沖縄・九州等の第2次世界大戦当時の米軍撮影航空写真を所蔵
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00162.html
・アクアプラネット済州~沖縄「美ら海水族館」とも縁の深い済州島最大の水族館
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00215.html