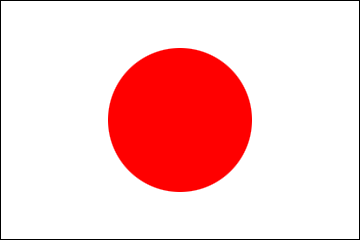済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!
令和3年3月31日
「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
 |
 |
井関至康総領事は、文化人類学者の玄丞桓(ヒョン・スンファン)済州大国語教育科教授にご案内いただき、済州島の伝統的な神事「チルモリ堂霊登クッ(チルモリダンヨンドゥンクッ)」を視察しました。玄丞桓教授は、司馬遼太郎氏の『耽羅紀行』でも登場された、泉靖一氏に招かれ留学した東京大学での研究の成果として『済州島巫俗の研究』を遺された故・玄容駿(ヒョン・ヨンジュン)済州大教授のご子息で、お父様と同じく、済州島の伝統的な巫俗研究の道を歩んでおられます。
アニミズムやシャーマニズムの伝統が強く残る済州は、「神口密度」も高い!
済州島は、韓国の一地域として儒教の影響を強く受けてきましたが、日本と同様、アニミズムやシャーマニズムの伝統が強く残っている地域であり、「1万8千」の神様がいるとされています。日本の「八百万」の神様と比べると数は少ないですが、人口1人あたりの「神口密度」は日本より高いです!と、比べて意味がある数字というよりは、どちらの数字も「とにかく多い」ということなんでしょうが…笑。朝鮮王朝の時代には、国教となった儒教の影響が強く、こうした済州の伝統的な信仰は「邪教」として排斥されたり、三姓穴で見たように、儒教式の祭礼を一部受け入れて折衷的なスタイルになったりもしました。また、その後も「非近代的な迷信」であるという批判も受けたりしたそうです。しかし済州島の人々は、この伝統を守ってきました。そして、故・玄容駿教授を含め文化人類学的な研究も進み、1980年にこの「済州チルモリ堂霊登クッ」が韓国の重要無形文化財71号に指定され、保護の対象となるや、済州各地に残る巫俗文化に対する見方は一転するに至りました。
済州で旧暦2月に行われる「チルモリ堂霊登クッ」とは?
「チルモリ堂霊登クッ」は、毎年旧暦2月に、済州市内の建入(コンイプ)洞の「チルモリ堂」で、地元の皆さんによって行われます(今回は新型コロナ対策ということで、屋内で人数を絞って行われました。)。「霊登」神は霊登国から済州島にやってくるという風神のおばあちゃん(ハルマン)、「クッ」は神と人を結ぶシャーマン(済州では神房=シンバンと呼びます)が執り行う巫俗儀礼を意味します。風神である霊登ハルマンは、毎年旧暦2月1日、冬の終わりの花冷えと、春の花の種を運びながら、済州島を訪れます。日本でいう「春一番」でしょうか?キャンディーズじゃなくて、おばあちゃんではありますが…。そして、漢拏山を含む済州島の大地と「海の畑」(海女さんによる漁が盛んな済州では、海女さんの漁場をこう呼びます)で種をまいた後、同15日に済州島を離れます。「チルモリ堂」では、同1日の歓迎祭、同14日の送別祭の2回行われますが、霊登ハルマンだけでなく、チルモリ堂の地元の神様、そして海の平和と大漁を司る竜神を祀るという、複合的な神事の性格を有しているということです。
根底に共通点がある 、済州と日本の「神様」を巡る伝統文化
済州島の「神様」を巡る伝統的な文化は、こうした神事の進行や衣装等々、個別の部分だけ見ると日本の伝統的な文化との違いも目に付きます。ただ、神房の皆さんの動きを実際に見てみると、日本の神事よりは多少リズムは早めながらも、身体の動かし方そのものは、多くの部分で似通っているようにも感じられました。玄丞桓教授によれば、済州と日本は、アルタイ・ツングースからの北方の影響、黒潮に乗ってやってきた南方の影響、そして道教の影響がミックスされたアニミズム・シャーマニズムを伝統文化の根底に有するという点で共通しており、また、そのバランスが全体として見ると大変似ているということです。済州の創世神話の地・三姓穴を訪れる日本からの観光客の皆さんが「雰囲気が神社に似ている」と感じるのも、こう捉えると自然なことなのかもしれません。また一つ、済州と日本の特別なつながりをそこはかとなく実感できる、素晴らしい機会になりました。
訪問関連フォト

△ご案内いただいた 玄丞桓(ヒョン・スンファン)教授とともに。ありがとうございました。

△静止画で恐縮ですが、実際に見ると体の動かし方その他、日本の神事と似ていると感じられるところも見受けられます。
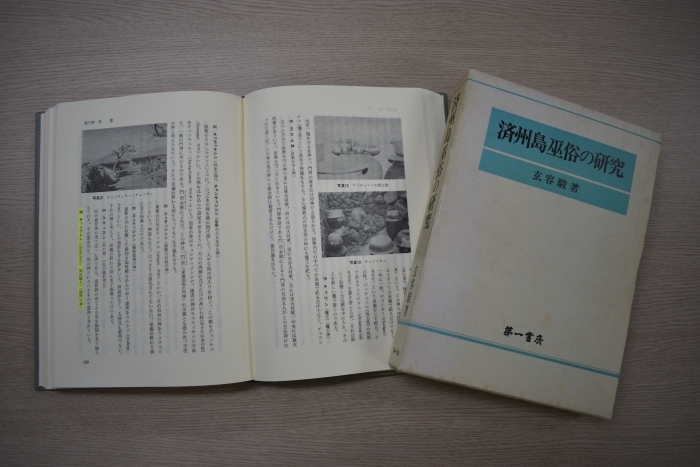
△故・玄容駿教授の東大留学の成果『済州島巫俗の研究』。神霊のあり方から儀礼の詳細まで、済州島の巫俗を東アジアの各地のそれとつぶさに比較した労作です。特についつい気になってしまうのが、「厠道婦人(チクトプイン)」という、済州島のトイレの神様に関する記述です。植村花菜さんのヒット曲(というか、歌に出てくるおばあちゃん)によれば、日本のトイレの神様の場合、トイレを毎日キレイにしたら、べっぴんさんになれるそうですが、『済州島巫俗の研究』によれば、済州島のトイレの神様は「たびたび祟ることがあるので、祟った時だけ祀る」のだそうです。新喜劇を録画し忘れたりしようものなら、大変な目に遭わされそうです…!

△例年であれば、このように屋外の「チルモリ堂」で行われます。済州ではそれぞれの集落に「堂(タン)」と呼ばれる、神様を祀る聖所があります。村の神様を祀る「本郷堂(ポニャンダン)」だけがあるところ(チルモリ堂も、建入洞の本郷堂です)、他の神様を祀る他の「堂」もあるところ等、集落によって様々で、形態も様々ですが、日本各地の鎮守の神様や、沖縄の御嶽(うたき)のような、集落の聖地とも雰囲気が似たところも感じられます。
なお、済州の集落では、「堂」とともに、「酺祭壇(ポジェダン)」という祭壇があるところも多いのですが、これは、儒教文化が入ってくるにつれ、村の男衆が「酺祭壇」で儒教式の村祭り「酺祭」を行い、女衆が「堂」での伝統的な村祭りを行うようになったものです。古代には男女が共同で村の安寧と豊作を祈る祭祀を行いましたが、今日の巫俗祭祀は女性が主導します。女性が中心になって伝統的な祭祀を司るというのは、日本の神社の巫女さんや、沖縄のノロ、ユタとも共通するところがありそうです。

△旧暦10月は日本中の神様が出雲大社に行ってしまうので「神無月」ですが、日本中から神様が集まる出雲では「神有月」と呼ぶそうです。この月の出雲の「神口密度」は、済州島と比べてもかなり高そうですね。
ところで、出雲大社は縁結びの神様で有名ですが、総領事によると、「神有月」の出雲大社にお参りしたら「めちゃくちゃ効いた」とのことです。果たして、どんな効き目があったのでしょうか?


△済州特別自治道は、青森県と姉妹都市の関係にあり、様々な面で活発な交流が行われてきていますが、青森県はイタコ文化でも有名ということで、シャーマニズムつながりの姉妹都市関係という側面もあります。夏の大祭でイタコの口寄せが行われる霊場恐山の写真です。
関連記事
・済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html
・済州野焼き祭り~野焼き文化で探る済州と日本のつながり
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00230.html
・漢拏山(ハルラサン)~日本の文化人類学のルーツのひとつを訪ねる
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00213.html
・三姓穴(サムソンヒョル)と婚姻址(ホニンジ)~済州誕生神話の舞台で探る日本とのゆかりと共通点
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html
・韓国の国家登録文化財「旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場」~日本で学んだ韓国最高の「蝶博士」にして、済州島研究の先駆者が初代所長
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00263.html
・「東日本大震災10周年行事」開催
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00225.html
・「2020年度済州こども絵画コンクール」を終えて
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00220.html