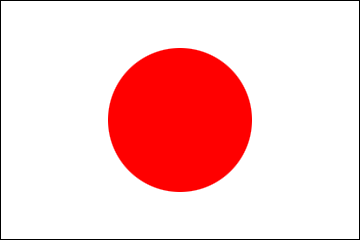韓国の国家登録文化財「旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場」~日本で学んだ韓国最高の「蝶博士」にして、済州島研究の先駆者が初代所長
令和3年5月18日
「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
 |
 |
井関至康総領事は、西帰浦市庁のオ・ソンハン都市課長、キム・ボンソク都市再生チーム長、オ・ホンブ霊泉(ヨンチョン)洞農村中心地活性化事業推進委員会委員長の案内を受け、2020年に韓国の国家登録文化財第785号に指定された「旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場」を訪問しました。
「旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場」が文化財指定された理由
旧京城帝国大学の生薬研究所は、済州島以外にもいくつかあったようですが、1930年代後半から40年代初めに建てられたという済州島試験場は、建築当時の姿がよく残されていて建築史的な意味が高いこと、ファザードの正面性を高めるためにポーチに表現された外装のディテールが特徴的であること等が、文化財指定の一つの理由となったそうです。そして、文化財指定の理由がもう一つ。韓国を代表する「蝶博士」であり、かつ「済州島学の先駆者」としても知られた、故・石宙明(ソク・チュミョン)氏が勤務した(1943年~45年)という、済州島の地域史の面での重要性です。
石宙明氏の鹿児島での運命的な出会い
1908年に平壌で生まれた石宙明氏は、日本で2番目の官立高等農林学校として知られた鹿児島高等農林学校(現・鹿児島大学農学部)に進み、運命的な出会いを果たします。1909年の同校設立とともに教授に就任し、九州帝国大学教授も兼任(1921~22年)し農学部昆虫学教室を設立、さらに後には日本昆虫学会会長(1942~44年)も務めた昆虫研究の権威、岡島銀次教授です。岡島教授の影響で昆虫研究に関心を持つようになった石宙明氏に対し、岡島教授はさらに「一つの分野で10年間集中すれば、その分野の専門家になれる」と、朝鮮半島の蝶研究の道を勧めました。75万匹もの蝶を標本にした石宙明氏の研究
石宙明氏は1929年に卒業後、当時朝鮮一と言われた施設を誇ったという開城(ケソン)の松都高等普通学校(旧制中学に相当)に生物教師として就職。10年以上同校に勤務しながら、恩師の言葉どおり蝶の研究に没頭し、最終的にはなんと75万匹の蝶を採集し標本にしました。他方、当時の朝鮮の蝶研究は、それなりの蓄積はあったものの、少ない標本数で少しでも形態が異なるものは新種として発表されていた状態だったそうです。石宙明氏は、圧倒的な採集数と、極めて緻密な形態比較という、今で言う「おたく」の王道を行く手法で、それ以前に新種とされてきたものを再整理し、その多くについて、分類学的には「同種異名」で新種とはいえないとして修正・除去。1940年に英国王立アジア学会朝鮮支会(The Royal Asiatic Society-Korea Branch)から、それまでの研究を集大成した英文論文『朝鮮産蝶総目録』(A Synonymic List of Butterflies of Korea)を発刊し、それまでは844種と分類されていた朝鮮半島の蝶を248種と修正したのです。日本の統治下にあった当時、朝鮮人学者が科学の分野で英語の研究書を発刊するのは、非常に珍しいことだったとのことです。石宙明氏が「済州島学の先駆者」と呼ばれるに至った理由
そして済州との関係です。1943年、旧京城帝国大学が付属の生薬研究所済州島試験場を開設するや、石宙明氏は、自ら志願して所長として着任。蝶の採集のために1936年のひと夏を過ごした思い出の地で、今度は約2年間過ごしながら、済州の文化と自然の研究に邁進しました。その成果は後に『済州島総書』と呼ばれる『済州島方言集』『済州島生命調査書』『済州島関係文献集』等の6冊にまとめられ、石宙明氏は「済州島学の先駆者」と呼ばれるに至りました。その後、石宙明氏は、韓国国立科学博物館の動物学研究部長に就任しますが、1950年、朝鮮戦争の戦火により、大切に保管していた全ての蝶の標本は灰燼に帰し、同氏自身も非業の死を遂げるに至ります。恩師・岡島銀次教授にも先立つ、約42年間の短い生涯でしたが、恩師の導きに沿って進む道を決め、日本のアカデミズムの場で鍛えた元祖「おたく」精神で蝶研究を究め、さらに済州島研究まで開拓した一生。そのゆかりの場を訪ね、済州と日本のゆかりの広さと深さに、改めて感じ入りました。
旧京城帝国大学付属生薬研究所済州島試験場の視察フォト

△建物については、設計者、正確な建設年ともに不明ということです。日本式の屋根瓦の小規模なコンクリート建築ですが、ファザードのポーチの柱には立派なタイルが使われ、小さいながらも「帝国大学の施設」であるという自己主張をしているかのようです。また、オレンジ色の瓦屋根も、済州島に設置する施設ということで、「南国」イメージを高めようという、設計者のこだわりポイントだったのでしょう。長らく済州大学亜熱帯生命科学研究所の一部として使われてきましたが、現在は、2020年の国家登録文化財指定を受け、西帰浦市としては今後、同研究所のリモデリングを通じて、石宙明氏の記念館にする方向で準備しておられるとのことです。

△すぐ近くには、石宙明氏を称える記念碑が建てられています。

△日本の「国蝶」オオムラサキ。1956年に日本初の蝶の図案の切手にオオムラサキが採用されたのを受けて、1957年に日本昆虫学会が選定したそうです。ただ、「国蝶」とはいえ、分布地域は日本だけというわけではありません。済州にもいないかな?と思って、漢拏山国立公園管理所に尋ねると、やはり棲息しているということで、上の写真を見せて下さいました。稀少なので、運が良くないと見ることは難しいそうですが…。
関連記事
・済州大学海洋科学研究所~海洋科学分野における済州と日本の交流の歴史
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00173.html
・済州大学地理教育専攻~沖縄・九州等の第2次世界大戦当時の米軍撮影航空写真を所蔵
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00162.html
・済州大学在日済州人センター~在日済州人を通じて見る済州と日本の関係史
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00140.html
・漢拏山(ハルラサン)~日本の文化人類学のルーツのひとつを訪ねる
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00213.html
・済州の神様を祀る「堂(タン)」~日本とも影響し合ってきた? 済州の民間信仰の舞台
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00272.html
・済州島に春をもたらす伝統神事「チルモリ堂霊登クッ」~日本の神様との共通性、「トイレの神様」もいます!
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00240.html
・三姓穴(サムソンヒョル)と婚姻址(ホニンジ)~済州誕生神話の舞台で探る日本とのゆかりと共通点
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html