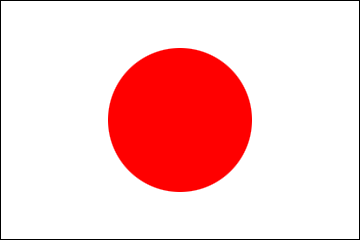済州グルメVol.10「うに」~済州の海女さんプロデュース、日本とのつながりが育てた済州の伝統食
令和4年5月23日
「済州と日本のちょっといい話」は、2020年4月から2022年7月まで2年4か月にわたり済州で総領事を務めた井関至康前総領事が、済州の様々な場所と人々に出会い、済州道民の皆様からの協力を得て、取りまとめたものです。多様な分野で長い間続いてきた済州と日本の深い関係に触れる一助となれば幸いです。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。
※「済州と日本のちょっといい話」の記事内容は連載当時のものであり、一部内容は最新の状況と異なる可能性があります。

済州では、海女さんが獲ってきた新鮮な生うにで作った「うにビビンバ」や「うにわかめスープ」といったうに料理を味わうことがよくあります。韓国本土等から済州を訪れる観光客にも人気が高いメニューですし、済州道民の皆さんも伝統食として誇りを感じておられるようです。済州道は特に近年、韓国でうに生産量トップとなることも多いですし、そもそも韓国の本土でうにが獲られるようになったのも、済州の海女さんが進出して獲るようになってからだと言われています。
そう思って、済州伝統飲食研究院の(ヤン・ヨンジン)院長に伺うと「いや、実は…」と、意外にも微妙な反応。済州の海女さんは昔からうにを獲って食べてはいたものの、(1)イガイガなので獲る時も痛いし身を剥くのも手間がかかる、(2)その割に身が小さい、(3)身はすぐ溶けてどろどろになるので保存も輸送も難しい、ということで、食べられる海産物を獲ることができなかった時にだけ獲って食べる物という扱いで、積極的に食べたくて食べていたわけではなかった、ということでした。
翻って、日本ではご存じのとおり「うに」と言えば、寿司ネタのエース格の一角を成す存在。このわた、からすみと共に江戸時代から「日本三大珍味」の1つに挙げられ、1799年の『日本山海名産図会』でも、うにの塩漬けを「これ塩辛中の第一とす」としつつ、現在の福井県の「越前うに」を高く評価しています。また、今日、日本のうに市場には、日本国内を含め世界中で取引されるうにの約7割が集まると言われています。
ということは、済州のうに料理が、済州道民が誇りを感じる伝統食にして、済州観光の代表食の1つにまで地位が向上したのには、どうやら、うに大国・日本との深い関係がありそうではありませんか!それでは済州のうにの伝統料理を食べてみましょうということで、井関至康総領事は、鹿児島大学で水産資源の研究で博士号を取得され、済州のうに事情に大変お詳しい、済州特別自治道海洋水産研究院水産種子研究課長の洪性完(ホン・ソンワン)博士と一緒に、済州道東部の吾照里(オジョリ)にあるうに料理がメインのお店「パダエチプ(海の家)」を訪れました。

済州のうに料理1「うにわかめスープ」

まずは「うにわかめスープ」を味わいます。わかめスープは韓国全土で広く見受けられる家庭料理ですが、以前紹介した甘鯛入りと同様、うに入りも済州のスペシャル料理。韓国本土で見かけることがあっても、そもそも韓国本土でうにを獲るようになったのは済州の海女さんが進出してからですから、元ネタは当然に済州道です。黄色のうにと緑のわかめという色合いも鮮やか。磯の風が口の中に舞い込んできたような風味も素晴らしいですね~。
済州のうに料理2「うにビビンバ」

次に味わったのは「うにビビンバ」。お店からは「コチュジャンや醤油を入れすぎないで下さい。うにの微妙な味が消えちゃいますんで…」と指導が入ります。韓国本土の濃い味付けに慣れた皆さんは、ついつい入れすぎちゃうんでしょうが、こちらは百も承知なので心配ご無用です。生うには、長距離の輸送に際しては身がどろどろに溶けてしまうのを防ぐのにミョウバンを入れることが多く、そうなると苦みが生じることもあるのですが、産地の済州でいただくので、そのような問題はありません。口に運ぶと、うにの爽やかかつとろりとした甘みと、ほんのり漂う香りがたまりません!
うに大国・日本と済州の深い縁
ところで、これらの済州のうに料理は、どのようにして、「海女さんが他の海産物が獲れない時期にだけ獲って食べる物」から、済州道民が誇りとする伝統食にまで登り詰めたのでしょうか?うに大国・日本でも、熱々のご飯との相性も抜群、日本酒の肴にも最高という「越前うに」のような塩漬けは昔から珍重されてきましたが、生うには放っておくとすぐに溶けてしまいます。うにの産地は別として、日本中で生うにを高級食材として食べることができるようになったのは、やはり輸送手段と冷蔵・冷凍技術が発達してからのこと。生うには、1950年代頃から鉄道による輸送が行われるようになり、さらに1975年頃から航空便で東京・築地に直送されるようになって、高級食材として扱われるようになってきたということのようです。
そして、済州のうに事情について。ここからは推測が混じらざるを得ないのですが、1965年の国交正常化を受けて1970年4月に済州の海女さん達の日本への出稼ぎが再開されるようになって以降、日本では生うにが高級食材として扱われるようになっていることを認識するようになり、済州でも、韓国本土への出稼ぎでも、うにを獲るようになっていきました。こうして済州で獲られたうには、済州と日本の直行の航空便(1981年済州・大阪便就航開始)等で日本に輸出もされるようになりました。さらに、韓国本土で寿司を含む和食が人気となり、韓国本土から済州を訪れる観光客も、うにを用いた料理を求めるようになってきました。このように、済州と日本との間の様々なルートでの交流を通じ、供給と需要の両面から、済州のうに、そして済州伝統のうに料理の地位と人気が、徐々に高まっていったのでは、と考えられます。
済州のうには、やはり日本と近いので、品種的にも日本と同じ物が獲れるようです。現在の主流はムラサキウニ。バフンウニも生息しているようです。また、日本では特に九州で最高級とされるアカウニも、量は少ないですが獲れるそうで、運が良ければ食べられるかもしれません。洪性完博士によると、2010年代の前半頃までは、済州のうにも日本に多く輸出されていたのが、済州での観光商品としての需要の増加や韓国本土での和食人気による需要の増加等で、近年は日本への輸出はほぼ途絶えたそうです。その一方で、済州沿岸での海女漁の収益に大きく貢献しており、特にうにの餌となる海藻が豊富な地域では、さざえを上回って売上額ナンバーワンとなっているところが増えているということです。
済州の海の生態系の課題に日本の知見が貢献

(写真提供:神奈川県水産技術センター)
こうしたうにを通じた済州と日本の関係について、最後にもう一点。近年、日本の海でも済州の海でも「磯焼け」と呼ばれる現象が大きな問題となっています。これは地球温暖化や、増えすぎたうにが海藻類を食べ尽くしてしまう等の原因により、沿岸の海藻が繁殖している藻場が衰退・消滅してしまう現象です。同じく海藻類を餌とするさざえやあわびも獲れなくなる、うにも海藻類が消えたために身が詰まっていないものばかりとなり、売り物にならなくなるという漁業面での悪影響は言うに及ばず、そもそも深刻な海の生態系の問題です。
この問題の解決策として、神奈川県水産技術センターが開発し、日本全国に広まったのが「キャベツウニ」という養殖手法です。規格外で廃棄対象となる地元産のキャベツをうにに与えて短期間養殖し、磯焼け対策とともにうにの品質向上も図るというものですが、この成功を見て、済州特別自治道海洋水産研究院も、キャベツを用いたうに養殖の実証実験に乗り出したそうです。済州道で養殖漁業に携わる皆さんからは、これまで日本の養殖技術を大いに参考にして発展してきた、というお話を伺うことが多々ありますが、うにについては、養殖漁業という面でも、海の生態系の問題への対応という面でも、日本の知見が貢献していたのでした!
関連写真

(写真提供:利尻町観光協会)
△うには日本全国の海に分布していますが、漁獲高が最も多いのは、済州道の友好協力都市である北海道。エゾバフンウニとキタムラサキウニを中心に、日本の漁獲高の9割近くを占めていますが、量もさることながら、味の良さにも定評があります。というのも、北海道は昆布の最高級品「利尻昆布」の産地。「利尻昆布」は、江戸時代には「北前船」で現在の大阪に運ばれ、料理のだしとして活用され、今に至る和食文化の基礎となってきました。その利尻昆布を食べて育ったうには当然旨い!ということのようです。

(「うに軍艦巻き」写真提供:琥珀)
△寿司屋さんでの憧れの存在「うに軍艦巻き」。回転しない寿司屋さんでは「時価」になっていることも多く、注文する際のプレッシャーはただならぬものがあります。そして、北海道・知床半島の「うにいくら丼(たこの卵入り)」。見るからにゴージャスな一品です…。

(写真提供:北東北3県・北海道ソウル事務所)
△済州道の姉妹都市・青森県も、うにを用いた郷土料理で知られています。八戸市と周辺の三陸海岸沿岸部に伝わる、うにとあわびのお吸い物「いちご煮」です。もともと漁師が浜で豪快に煮て作るような、日常的な家庭料理だったのが、時代の流れでうにやあわびが高級食材として扱われるようになり、現代では結婚式やお正月といった祝い事に欠かせない料理として大切に受け継がれているということです。なお、「いちご煮」と呼ばれるのは、いちごが入っているからではなく、椀に盛り付けたとき、あわびなどのエキスで乳白色に濁った汁に浮かぶ黄金色のうにが、まるで朝露にかすむ野いちごのように見えたことから名付けられたそうです。

△日本人の「うに」に対する思いは、並大抵のものではありません。もしかしたら意味が分からないかもしれませんが、「うに」が主人公の漫画さえ存在します…。興味がある方は、インターネットで検索してみて下さい…。
写真は、漫画で吹き出し等に使われるもので、日本の漫画用語では「ウニフラッシュ」(略して「ウニフラ」)と呼ばれているそうです。
関連記事
・済州グルメvol.6「甘鯛」~日本の高級食材は済州を代表するソウルフードhttps://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00350.html
・済州グルメvol.4「あわび」~渋谷の韓国料理店のルーツ「吾照里(オジョリ)」で探った済州と日本の関係
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00314.html
・済州グルメvol.3「ハンチ(剣先イカ)」~済州の夏の風物詩と佐賀県唐津市名物「呼子のイカ」の深い縁
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00290.html
・【コラム】東京オリンピック・パラリンピック開催~済州のスポーツと言えばゴルフ!日本とのご縁を探ってみました!
https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00285.html