|
海女文化との出会い |
| |
| 在済州総領事館総領事 余田幸夫 |
| |
|
| |
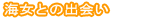
世界自然遺産を有する「世界平和の島・済州」に赴任してから既に1年10ヶ月。この間,済州の人々,民俗文化,自然等から私は多くの刺激を受け続けている。そのうちの一つが韓国と日本にしか存在しない海女文化である。
済州に着任して1ヶ月後のある日曜日,竜頭岩付近の岩場に腰を掛けて海を眺めていると,後方から女性たちの迫力ある声が聞こえてきた。済州の方言なので殆ど内容は理解できない。振り向くと黒や紫色等のゴム潜水服を着て海女5人が,さっそうと海辺の方に降りてくる。 チラッと顔に目をやると,皆年配の方々。頭に水中眼鏡,腹部に重りを付け,肩には網の袋(日本語でスカリ)と浮(ウキ)を掛け,手には磯ノミやヤス(魚とりの道具)と足につける水掻きを持っている。目の前で海女を初めて見た私は,いささか興奮気味。
彼女たちは水中眼鏡を顔にあて,準備万端,そして浮を両手で前に突き出して海に入る。私は目の前の海で展開される海女二人のムルチル(潜水作業)に釘付けになる。二人は同時に頭を水中に入れるや4本の足が海面に現れ,直ぐ勢い良く海中に消える。海面に残っているのは赤や橙色の鮮やかな浮のみ。暫く静寂が続いた後,突然水面に二人の頭が浮かび,同時に,「ピュー」と小鳥の鳴き声のような心地よい音が聞こえる。これは体に負担を掛けないために徐々に吐き出す呼吸法から出る音だと聞いた。そして収穫物である海底の貝や魚等を網の袋に入れる。この一連の動作を二人が一緒に何度も何度も繰り返す。二人の息がぴったりで,一見,シンクロナイズド・スイミングを見ているような錯覚に陥るが,それ以上に神秘的なものを感じさせられ,ついつい凝視してしまう。この時以来,私は海女に取り付かれてしまった。

済州は「三多の島」として知られる。風と石と女性。年間を通じて風が吹き,火山島なので奇岩怪岸はもとより家屋や田畑や墓地の周りの石垣等,多くの石で独特の風情をかもし出している。女性は数が多いと言うよりも,昔からその存在感が大きかったということだと思う。厳しい自然と闘い,家事や子育てはもとより,昼間は海でムルチルか畑で仕事,一日中休む暇なく働き続ける忍耐力と生活力のある素晴らしい女性像を意味しているようだ。
昨年の春,東側の海岸道路をドライブしながらエメラルドグリーンの海を眺めていたところ,突然,目の前に100名程の海女集団が現れた。「海女の小屋」の周りからは楽しそうな大きな笑い声が聞こえる。しばらくすると,いっせいに立ち上がり,潜水用具を持つ海女集団が海岸道路を堂々と,かつ悠々と闊歩し始めた。潮の流れや風の状況等を観察しながら海に入るタイミングを考えるそうだ。そして海女達は10数名づつのグループに分れてそれぞれ定められた海辺に降りていく。各地点から,一人づつ数珠繋ぎのようになって遠くへ泳いでいく。青々とした海一面に各入水地点から色とりどりの浮が鮮やかに広がって行く。そして休み無く4~5時間にもわたる壮大なドラマを展開する。大自然と人間の見事なハーモニーであり,これは芸術だと感じた。
ところで,「海女の小屋」の周辺にはカラフルな新品のオートバイ等が所狭しと並んでいた。海女たちが自宅から乗りつけたもので,恐らく十数年前まではこのような交通手段は想像できなかったのではなかろうか。更に注目すべきは,海女たちが持参してきた籠が,バイクの荷台や小屋の周りに放置されていること。その籠には飲み物のボトルや風呂敷包みなどが入っているが,その辺には警備員も見張りも誰もいない。この光景は,済州島が三多の島であると同時に「三無の島」,すなわち「泥棒,門,乞食」の無い平和な島であることを改めて実感させる。年々増大する外部からの旅行者は,この美しい三無の島を決して汚さないようにすべきだと思った。

私が親しくしている済州生まれのあるプロの写真家は,済州島のみならず慶尚南北道や全羅南北道の海岸でムルチルしている済州出身の逞しく生命力溢れる海女の素晴らしい姿を白黒フィルムに収めている。しかし,済州出身の写真家とはいえ,彼女たちの海女の姿や生活を自由に撮影するためには,事前に多くの時間と労力が必要だったと言う。なぜなら,海女達をあたかも見世物であるかのように,近くで興味本位にガシャガシャとシャッターを切るような心無い礼を欠いた行為に対し,彼女達は不快感を禁じえない等,様々な事情がある由である。何事もそうであるように,お互いが胸襟を開いて直接話し合ってこそ真の姿が見えるようになるということだろう。当地のある新聞記者が「海女の写真を撮りたければ,事前に了承を得るべきだ」と私に教えてくれたことがあるが,その通りであり,特に観光客は留意すべき点だと思う。
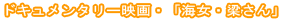
海女の映画で思い出すのは「人魚公主」で,女優・田ドヨンが二役を見事に演じ,多くのファンを魅了した。一方,あまり知られていないが,「海女・梁さん」と題するドキュメンタリー映画がある。この主人公・梁さんは今95歳で,日本の大阪で元気に過ごしておられる。このドキュメンタリーは実話であるだけに見る人に大きな感動を与える。時代に翻弄され,梁さんはお子様が韓国・北朝鮮,そして日本の三つに別れ別れになる等,悲運の運命を辿ったが,日本で海女を続けながら,逞しい生命力と限りのない愛情で子育てをはじめ多くの問題を克服された。正しくそこに済州のオモン(母)の真髄をみる思いがした。未だ御覧になっていない方は,是非一度この映画を鑑賞されることをお勧めしたい。
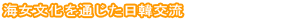
済州の東部に立派な海女博物館があり,海女のムルチル関連道具や生活習慣,食事,家をはじめ済州を理解する上に大いに助けとなる。海女の人口は減る一方と言われているが,現在,現職および前職がそれぞれ約5300人,合計約1万600人と言われ,年齢的には50歳代以上が9割強を占めている由。日本でも激減して今では全国3千人程度と言われる。この貴重な海女文化を絶やすことなく継承していくためには,後継者の養成が必要であり,済州道では海女学校が設立された。
日韓双方では,海女に関するシンポジウムが毎年開催されており,海女の相互交流も実現し,日本の三重県鳥羽市の海女が使用している道具の寄贈や海女写真の相互展示会等,様々な交流が活発化していることは素晴らしいことだと思う。済州の海女の歌「イヨドサナ」は,単調なようではあるが,何度聴いても飽きない不思議な魅力がある。最近では,日韓双方で海女文化を世界文化遺産として登録すべく努力中であり,遠くない将来実現することを願っている。
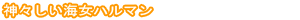
昨年秋,ある週末の夕方,世界自然遺産の「日出峰」辺りの海辺を家内と散歩していると,直ぐ近くにたった一つの白色の浮が見えた。そして30分くらい経過してムルチル作業も終わり,その海女は海辺の岩の上に収穫した海産物が一杯入った網袋を引っ張り上げた。薄暗くてその女性の顔はよく見えないが,小柄でか細い体で腰がかなり前屈みの老婆であった。そしてその大きな網袋を背中に負い,90度位に腰を曲げて夕陽を背にしながら砂浜を横切り,やがて草むらの中にその姿は消えた。その老婆の後ろ姿は,神々しくさえあり,そして思わず心の中で合掌した。済州島は,1万8千の神々がやどり,神話や伝説の宝庫と言われる。近年国際自由都市を目指して急速に発展を続けている済州島。それだけに済州独自の貴重な民俗文化を一層大切に保存し発展させていくことが重要だと思う。
|
| (了) |
|